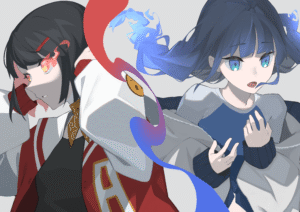三章〜指輪〜
『ねぇ~おじいちゃん! これ仁美にちょうだい!』
幼い頃。
その指輪はなぜか特別なものに見えた。
おじいちゃんは穏やかな笑顔で、私の頭をやさしく撫でる。
『仁美には、まだちょっと早いかもしれないね』
『なんで! なんで!』
『ほら、今はぶかぶかでつけられないだろう?』
おじいちゃんは私の薬指にそっと嵌めてくれた。
でも指輪はするりと抜けて、そのまま床に落ちてしまった。
『……つけられない』
指輪を拾い、今度は自分でつけようする。
でも結果は同じ。
指輪は指を抜け落ち、涙で視界がにじんだ。
私の目線に合わせるように、おじいちゃんがゆっくりとしゃがみ込んだ。
そして、指輪をそっと手に取る。
『将来、仁美が素敵な女性になるその日まで、おじいちゃんが預かっておくよ』
おじいちゃんの大きな手が、私の頬の涙をやさしくぬぐった。
『絶対? 仁美が大人になったら、指輪くれる?』
『あぁ、約束するよ。仁美が素敵な女性になったらね』
『やったっ! あたし、絶対、すてきなじょせいになる! おじいちゃん、約束ね!』
おじいちゃんは目を細めて微笑んでいる。
その笑顔が、子どもの私には、世界でいちばん優しい光に見えた。
――――――
指輪の記憶が仁美の頭の中へ流れ込んでいた。
仁美は茫然と立ち尽くしている。
「そうだ……あの指輪……」
仁美の目に涙が浮かんでいた。
私は思わず、目をそらす。
祈祷師には、付喪神と人間を繋ぐ役目もある。
想いを宿したモノの声を、時に映像や言葉として〝 受け継ぐべき人〟に伝えること。
それが、私の仕事のひとつだった。
「おじいちゃん子だったんですね」
声を掛けると、仁美はひとつひとつ思い出すように静かに話し始めた。
「私、両親が早くに亡くなってね。だから、おじいちゃんに育ててもらったみたいなものなの。けど、まぁ色々あって……もう十年以上も会ってなかったわ」
仁美は手のひらで指輪を見つめながら続けた。
「一人になった私を育ててくれた恩はあるし、最後くらいは面倒見ようかなって」
「……優しいんですね」
そんな当たり障りのない言葉しか出てこない自分に少し嫌気が差した。
「……そんなんじゃないわ」
仁美が指に付けているデジタルリングに触れる。
すると、その光がふっと消えた。
「おじいちゃんとは、どうして疎遠になっちゃったんですか?」
「……」
「あ、えっと……答えたくなければ無理にとは……」
「あなた、デリカシーないって言われない?」
「は、はは……よく、言われますね、友達に……」
仁美は一瞬迷ったあと、観念したように話し始めた。
「……私が中学に上がるくらいの時からおじいちゃん変わっちゃったの。優しかったおじいちゃんがすごく厳しい人になって。勉強しろとか、料理しろとか、掃除洗濯、全部私に押し付けてきて。私も中学生だったし。友達とも遊びたかったのに」
「…………」
「それでね、死ぬ気で勉強して、特待生で松商学園に入学したの。松商の特待生なら無料で寮生活が出来て、授業料も免除だったから」
仁美はこちらを振り返ることなく続けた。
「高校に受かって、家を出るときに言ってやったの。二度と帰ってこないから! おじいちゃんの顔なんて二度と見たくないって」
仁美はなんとも形容しがたい表情を浮かべていた。
悔しさとも、後悔ともつかない、心の奥から湧き上がる何かを押し殺しているようで。
声をかけてあげたかったが、何て声をかけるのが正解なのか分からなかった。
こういう時に優しい言葉がかけられる人間になれたら……。
「あの、一緒に深志神社に行きませんか?」
沈黙をごまかすみたいに、そんなことを口にしていた。
「え?」
「私、神社って好きなんです。空気が澄んでいるというか、心が少し軽くなる気がして。気持ちが沈んでるときとか、よくお参りに行くんです」
「神社……そうね」
仁美は少し考えるように間を置いてから答える。
「実は私も、行きたいなって思っていたところだったの。どうしてかは、分からないけど」
不思議な事もあるものね。
そう言って、仁美は小さく笑った。