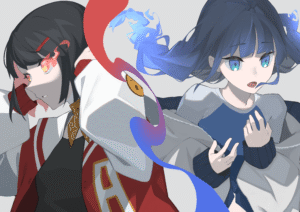――想いは、唄で還せるんだよ。
いつか聞いた声が、ふと頭の奥でささやく。
それは決して忘れることのできない――
私にとって何よりも大切な記憶。
「……ごめんね。いつか還してあげるから」
私は何度目かも分からないその言葉を口にする。
薄暗い神社の本殿。
私は静かに祈りの言葉を口にした。
その瞬間、左目に淡い炎が宿る。
呼応するように目の前の想いが静かに光を帯びた。
その光はゆらりと揺れ、やがて風に溶けるように静かに消えていく。
それは何度も見てきた、変わらない景色。
「あの、朱璃さん……?」
隣から不安を隠しきれない声が聞こえた。
私はゆっくりと顔を上げ、いつもの作り慣れた笑顔を浮かべる。
「この子は、私が責任を持って、然るべき場所でお預かりします」
そう言葉を口にするたび、喉の奥に鉛のような重さが沈んでいく。
視線を落とすと、彼女の指先が小さく震えていた。
「……ありがとうございます」
と小さな、震えた声。
その声に滲んでいた想いを、私は聞き取れないふりをした。
あれから、どれだけ多くの想いに触れてきただろう。
私にできたのは、せめて穏やかに眠れるようにと願うこと。
そして、その想いを鎮めることだけだった。
そのたびに、胸の奥で何かがひとつ、またひとつと冷えていく。
鎮めることしかできない――
でも、いつかその想いを還すことができるように。
それは誰もが笑うような夢。
その夢は、私の願いになった。
依頼を終えた夜、私はいつもの店へ向かった。
古びた看板の下で立ち止まる。
扉の向こうから、かすかにR&Bが聴こえてくる。
店に入ると、焙煎豆の香りと低いベースラインがふわりと混ざり合った。
店長がカウンターで紙の本をめくりながら顔を上げる。
「終わったのか」
「うん、さっき終わったところ。……この子、見てくれる?」
私は手の中にあるそれをテーブルに置いた。
店長は黙って手に取り、ひと目で判断する。
「……ないな。時代が違う」
予想通りの答え。
わかっていた。それでも、確かめずにはいられなかった。
「だよね~。一応聞いただけ」
笑顔を浮かべ、いつもの調子を装う。
「店長、次の依頼ある?」
それに、店長は驚いたような、呆れたような表情を浮かべた。
「お前な……いま終えたばかりだろ。少しは休め」
「こんくらい余裕だって。店長は心配しすぎ~」
依頼書の束に手を伸ばすと、店長が慌てて声を上げた。
「おい、こら勝手に取るな!」
「隙あり! じゃ、これ行ってくるね」
背中越しに響くため息。
それを聞きながら、私は逃げるように店を飛び出した。
私は信じている。
唄があれば、想いは還せる。
この手では届かなかった願いも、
唄があれば、きっと還せると。
――だから私は、唄を探し続ける。