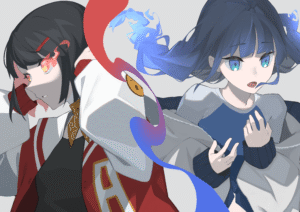一章〜邂逅〜
深志神社は「天神様」と呼ばれ、地元で親しまれている。
依頼人の家は、そこから程近い閑静な住宅街にあった。
数ヶ月前、そこで暮らしていたおじいさんが亡くなったという。
お孫さんが遺品の整理に訪れたところ、不可思議な現象が起き始めたらしい。
突然、花瓶や蛍光灯が割れたり、地震でも無いのに家が揺れ動いたり――。
遺品整理を進めることができず、周りからの勧めで深志神社へお祓いに行った結果、ANIERAを紹介された。というのが今回の依頼に至る顛末だった。
「老後の一人暮らしって寂しいのかな? 私はレコードに囲まれてのんびり出来るならアリだな~。ぐふふ」
これだけの家なら壁にコレクションのレコードを飾ることだって出来るだろう。
そう思いながら、門をくぐり、庭を歩く。
「本当に広い……これ全部この人の土地なのかな」
庭はぱっと見でも百坪くらいはありそうな広さで、大きな池や庭石が置かれている。
その奥に立派な蔵造りの屋敷が構えていた。
今は雑草に覆われてしまっているが、おそらく昔は立派な庭園だったのだろうことがわかる。
私は玄関のインターホンを押した。
「はーい」
奥の方から女性の声が聞こえ、しばらく待つとガラガラとドアが開いた。
「えっと、もしかして」
玄関から現れたのは、ショートヘアを柔らかく茶色に染めた、今どきの可愛らしい女性だった。流行のAR(拡張現実)パンツ に、腰丈のニットを合わせた軽やかなスタイルがよく似合っている。
ARパンツは、2045年頃に発売されたAR技術を活用した最新ファッションだ。
スマートフォンに変わって登場した次世代ウェアラブルデバイス「Skylim(スカイリム)」に専用アプリをインストールすることで、その日の気分にあわせてパンツの模様――エフェクトを自由に切り替えることが出来る。
十代から二十代を中心に爆発的な人気を誇り、限定エフェクトは相場の十倍以上で取引されているらしい。
私はそもそもSkylimを持っていない。SkylimもARパンツも目がチカチカするから無理! と友達に話したら、おばあちゃんかよ! とつっこまれてしまった。
うら若き乙女に向かって酷い事を言うものだ。
「ANIERAの依頼で派遣された祈祷師の安野朱璃です」
「そう、あなたが……私は二村仁美。よろしくね」
「……おうちにいて大丈夫だったんですか?」
「どういう意味?」
「あ、えっと、深い意味はないんですけど、他の依頼者さんとかは怖がって家に居たがらない事も多いので……」
「平気よ、私はそういうのを信じてないもの」
「そ、そういうの……?」
「霊とかオカルトとか。今回は周りに言われて仕方なく連絡したけど……」
「は、はは」
「それより、祈祷師と聞いた時はもっと年寄りが来ると思ったんだけど、あなたいくつ?本当に大丈夫なのよね?」
「お任せください! これでも一応、天才祈祷師としてやらせて頂いております」
「……余計に不安なんだけど……まぁいいわ。とりあえず入って」
「はい! お邪魔しま〜す」
不安そうな顔をした仁美を横目に、私は靴を脱いで家に上がった。
屋敷は平屋作りで天井も高く、中に入るとより一層広く感じる。
玄関から真っ直ぐ伸びる廊下は長すぎて奥までよく見えない。
まるでどこか別世界に繋がっているように思えた。
「庭もですけど、本当に立派なお屋敷ですね」
「そう? 広いだけよ」
仁美は足早に廊下の奥へと進んでいく。
私はそそくさと脱いだ靴を整え、仁美の後を追った。
薄暗い長い廊下の突き当りを右に曲がる。
そこには両引き戸の部屋があった。
「ここよ」
仁美が障子戸を開けると、二十畳ほどの畳部屋が広がっていた。
おそらく、かつては仏間だったのだろう。
古びた丸机と座布団、その奥には仏壇と化粧箪笥が並んでいる。
仁美が半信半疑といった表情で、ゆっくりと私の方を振り返った。
「どう? 何かわかる?」
「まだなんとも……ちょっと詳しく調べさせてください」
「……何も無いと思うわよ」
私は畳部屋に入り、改めてあたりを見渡した。
目に見えて不自然な様子はない。
目を瞑り、呼吸に意識を集中させた。
徐々に周りから音が消えていく。
――どこにいるの? おしえて。
すると、暗い視界の中に淡い光がぽつりと灯る。
その光を放っていたのは、部屋の隅で誰かを待つように佇む、化粧箪笥だった。
「仁美さん、この化粧箪笥、開けても良いですか?」
「え? あぁ、どうぞ」
私は慎重に一番上の引き出しを開ける。
中には年代物のネックレスが入っていた。
「あ、これ! VAN CLEEF & ARPELS のネックレス! 年代物ですね~かわいい!」
口走ったあと、ハッとして仁美を見る。
好きなものを見つけて、つい興奮してしまった。
「あなた、若いのに良い趣味してるわね。いまどき、シルバーのアクセサリーなんて」
「は、はい! それで友達とも話合わなくって、へへ」
「よかったらあげるわよ」
仁美はそう言った後、指に付けている最新のデジタルアクセサリーの指輪を見せつけてきた。
「良いでしょ? 先月の給料で買ったティファニーの新作。その日の気分に合わせて色を変えられるの」
指輪の中で青と水色のグラデーションになった水のような光が、彼女のARパンツと連動してゆらゆらと揺れている。
普通の宝石や装飾品ではありえない輝きを宿していた。
私は「可愛いですね」とだけ言って、二段目、三段目と引き出しを開けていく。
中には他にもアクセサリーや化粧道具が入っていた。どれも丁寧に保管されていて、大切にされていたことがわかる。だが、どれも変わった気配は感じない。
一番下の引き出しに手をかけた瞬間、指先からピリッという確かな気配を感じた。
ここか……と、改めてゆっくりと引き出しを開けると、年代物の青い指輪ケースが入っていた。
「これですね」
私はその指輪ケースを取り出し、仁美に見せる。
「なにそれ? 指輪ケース?」
「はい、これが今回の原因です」