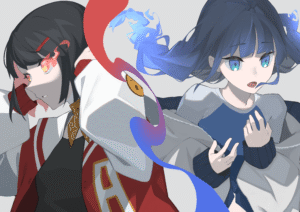二章〜陌霊〜
「原因? これが……?」
仁美は指輪ケースをまじまじと見つめている。
「見覚え、ありますか?」
「……あるような、ないような」
「中見たらわかるかもしれませんし、開けてみましょう」
私はそういって指輪ケースの口に指をかけた。
その瞬間、部屋が暗くなり、空気が冷たく、そして重くなる。
指輪ケースから鋭い光が漏れだしていた。
「仁美さん! 下がって!」
私はやむを得ず、仁美を突き飛ばした。
その弾みで指輪ケースが手から滑り落ちてしまう。
「いたっ! ちょっとなにすん……」
その異様な光景に、仁美は息をのみ、言葉を失った。
指輪がケースから飛び出し、激しい光を放ちながら宙に浮いている。
「ねぇちょっと……何が起きてるの……」
「やっぱり……陌霊化しかけてる」
「ばくれ? なに? なんなのよそれ……」
指輪は光を放ちながら、徐々にその形を変えていく。
光が徐々に弱まり、かつて指輪だったはずのものが姿を現した。
全長二メートルはある黒い二足歩行の狼のような何か。
その体は未だ形が定まらないようで、炎のように揺れている。
「ガルル…………」
低い呻き声をあげ、その目がこちらを威嚇するように睨んできた。
その様子は苦しんでいるようにも見える。
「ひっ……」
「そこを動かないでくださいね」
仁美は答えず、首を何度も縦に振った。
私は深く息を吸って、黒い〝それ〟に向きなおって構えをとる。
「まだ間に合えばいいんだけど」
一瞬の沈黙。
天地同根 万物同体
左目が熱くなっていく。
黒いそれは大きな牙を剥き出しにしながら、飛びかかってきた。
単純で直線的な攻撃。
私は重心を右に傾け、ひらりとかわす。
黒いそれは勢いを殺せず、激しく壁に激突した。
「痛そー、大丈夫? そのままちょっと大人しくしてもらおっかな!」
私は黒いそれの懐に入り込み、祝詞を唱える。
我が清浄を似て
九十九の汚穢を打祓わん
私は祝詞を唱えながら、渾身の右フックを放つ。
「グアッ……」
黒いそれは炎のような光に包まれ、低い唸り声をあげながら、その場に倒れこんだ。
徐々にその姿は見覚えのある指輪に変わっていく。
「まだ自我が残っていてくれて助かった、ありがとう」
私はその指輪を大切に拾い上げ、仁美の方に向きなおった。
「大丈夫ですか? 怪我はありませんか?」
「バケモノが……朱璃さん……目が……燃えて……」
仁美はまだ何が起きたのか分からないと言った様子で、虚空を見つめている。
「仁美さん!」
「あ、えぇ、なんだったの……本当に」
仁美は目をぱちくりさせて、私の方を見た。
「これで大丈夫です」
「これって……どうなって……?」
戸惑いを含んだ声が静かに響く。
その問いには答えず、私は話を続けた。
「付喪神って知っていますか?」
仁美は知らないと首を横に振った。
予想通りの答え。
私たちのように特別な修行を積んだ祈祷師でなければ、見ることも声を聞くこともできない。
「長い間、人の思いや信仰に触れた〝モノ〟は魂を宿し、付喪神と呼ばれる存在になります。付喪神は、人の想いが具現化した存在。だから、人の優しさに触れて顕現した付喪神は、守り神のような存在となります」
「現実に、そんなことが……」
「でも、人の悪意に触れたり、持ち主がいなくなったり、信仰が弱くなったりすると……付喪神は陌霊となって、人に災いをもたらすようになるんです」
「陌霊。じゃあこの指輪も……」
「この子は、良い付喪神ですよ。代々、大切にされてきた指輪なんだと思います」
「ほんと? ……大丈夫なの?」
「はい! 私たち祈祷師の役目は陌霊化する前に封印して、あるべき世界に還してあげることなんですが――」
今はまだ、封印までしかできないけど、いつかきっと。
「このまま封印されないってことは、仁美さんに何か伝えたい事があるんだと思います」
「……私に? 何を?」
「それを聞くべき人に伝えるのも、私たち祈祷師の役目なんです」
そういって私は手に持っていた指輪に目をやる。
「――あなたの想いを教えて」
そう囁くと、指輪は淡い炎に包まれた。
「え、なに? また?」
仁美は逃げるように指輪から距離を取った。
「大丈夫です。仁美さん、私の手を握ってもらえますか?」
「……わかったわ」
仁美は少し考えた後、意を決した様子で手を伸ばす。
やっぱりまだ自我がある。この子は大丈夫だ。
「いいよ」
私はそう呟いて、仁美の手を強く握った。